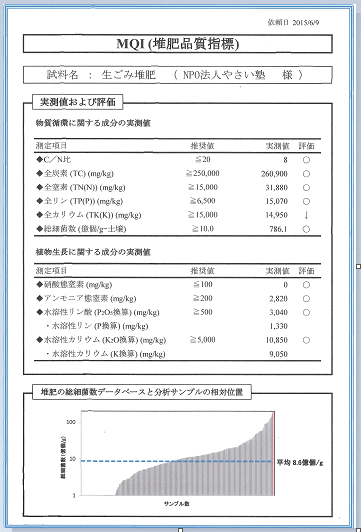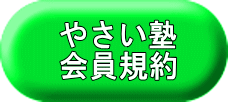活動状況
2023年度 活動状況
<活動概要>
1)NPO法人やさい塾を解散し、やさい塾同好会へ移行しました。
2)令和5年度 環境おかやま大賞の受賞 (2023年12月23日)
やさい塾が「環境おかやま大賞」を受賞しました。約10年間の活動が公的機関の岡山県に認められた。受賞は大変に嬉しく、自信をもって我々の活動が続けられる。以下、受賞理由です。
<功績>100歳でもやれる「持続可能な家庭菜園」をテーマに段ボールコンポストの普及活動に取り組んでおり、市民への環境問題への意識づけや興味喚起に繋がり地域における廃棄物のリサイクルと家庭の生ごみ減量化に貢献している。
3)YouTubeによる「サステナブルな家庭菜園」の普及活動
2023年5月➡視聴回数35万回、チャンネル登録者1,708人
2024年5月➡視聴回数65万回、チャンネル登録者2,708人
2022年度 活動状況
<活動概要>
やさい塾は、サステナブルな家庭菜園を通じて、無農薬で安全でおいしい野菜を作り、1アールの広さの菜園を使って、1世帯3人家族が必要な野菜を自給することを目指している。家庭から出る生ゴミをダンボールコンポストで堆肥化し、その堆肥と米糠を使って、年間40kgの生ゴミボカシ肥を作り、この肥料を使えば1アールの菜園で必要な野菜を作ることができる。この持続可能な家庭菜園の技術を約10年かけて確立し、2022年1月からは、YouTubeやLINEなどのツールを使って情報発信している。やさい塾の目標は、この技術を広く一般に普及させ、多くの人々が自宅でサステナブルな家庭菜園を楽しめるようにすることであり、無農薬で安全な野菜を作るだけでなく、地球環境の保護にも貢献する。NPO法人として10年間の活動を継続し、安心安全な野菜づくりや生きがいづくり、そして持続可能な家庭菜園に向けた目標にも近づくことができた。やさい塾YouTubeチャンネルの開設により、この技術を広く一般の人へ普及させることができ、チャンネル登録者数1600人、全動画のアクセス総回数は30万件に達し、普及活動の目的を達成しつつある。しかしながら、NPO法人を運営するためには、電話やインターネットなどの通信費用が必要であり、また会計処理や法人登記、県への報告など法的責任も発生するため、これらの費用と責任を負担することは会員の高齢化もあり、難しくなってきた。よって、当初の目的を達成したため、NPO法人としての活動を終了する決断をしました。令和5年4月22日の総会にてNPO法人の解散決裁を致します。そして新たに「やさい塾 同好会」を2023年5月より発足させ、活動を継続していきます。
2021年度 活動状況
<活動概要>
本年度は、変異株のデルタ・オミクロンの出現、感染拡大でやさい塾定例会は殆どが中止になりました。そこで、昨年度からWebで実施している「家庭菜園の通信講座」で野菜づくりのタイムリーな動画配信を継続して行いました。現在、塾生及び講座生は井原市を中心に笠岡市、矢掛町、岡山市、倉敷市、県外では広島県福山市からの参加です。全国的には関東の埼玉県熊谷市からの講座生がいます。会員数も約50名近くに増加しましたが、現在の情報発信では普及活動の限界も見えてきました。そこでコロナ禍ではYouTubeの視聴が広く一般の人へPRするには有効であると考え、やさい塾YouTubeチャンネルを開設しました。「やさい塾」チャンネルアクセス数13,565 チャンネル登録者数111名(令和4年3月現在)
安心・安全な野菜作りの調査・研究では雑草農法ともみ殻農法について、モデル菜園で検証試験を実施しました。その結果、通常の有機肥料と同じくらいの野菜が収穫できることを確認できました。ただ、未だ、虫食いの被害があるので、改善策を考えて来期も継続して検討します。
野菜作りにおいて、炭の施肥が重要だと色々な情報より分かってきました。炭の中でもモミガラくん炭は施肥実績もあり野菜作りには有益ですが、くん炭製造時に人体や環境に良くないガスを発生します。そのモミガラくん炭の代替として竹炭、木炭が有効です。その竹炭、木炭づくりに無煙炭化器が有効であるこが前年度判明していましたので、その動画をYouTube等で発信しました。持続可能な家庭菜園のマニュアルをもとに、現地で土作り指導を行いました。マニュアル通り実施できれば野菜づくりが可能か検証していきます。
YouTubeにて、「やさい塾のサステナブル(持続可能)な家庭菜園を!」動画の紹介でアクセス数200あり、多数の方に視聴されています。生ごみ堆肥作りのダンボールコンポストでは延べ1500のアクセス数です。環境や持続可能な取り組みに関心があることが分かり、YouTubeの発信に手ごたえを感じています。
2020年度 活動状況
<活動概要>
今年度は新型コロナウイルスの感染拡大が続いたために「定例会」「家庭菜園講座」を一度も開催出来ませんでした。しかし、ウイズコロナに即応するため、リモートによる野菜作りの指導や定例会・講座に切り替えて行いました。
ボカシ肥作りの詳細な作り方、ダンボールコンポストは完成までの様子、野菜作りはタイムリーな菜園の作業を動画配信して行きました。
これらの方法は、今までは出来なかった部分でもあり、思い付かなった所でもありました。作業のお手本をタイムリーに配信する方法は、植付けの時期や方法が詳しく分かり、なかなかの好評価でした。またLINEノートの優れた所は、LINE上にデータ、動画が半永久的に保存され、検索も簡単、見たい時に自分のペースでいつでも見れる所です。
そして、次に行ったのがLINEのグループ通話での定例会や講座のQ&Aです。最初は中々、慣れなかった人も徐々に参加出来ようになって来ました。今年一年でLINEによる動画配信は217本を達成し、配信・撮影ノウハウの知見が得られました。また会員の皆様の支援も頂き、会員数の減少も無く運営が出来ました。
<今後にむけて>
2019年度 活動状況
<活動概要>
本年度のトピックスは「野菜作りにAIスピーカー(アレクサ)の利用」を導入したことです。Amazon Echoアレクサには色々なスキル(機能)の「天気を教えて」「おはよう」「ニュースを聞かせて」「音楽を聞かせて」「タイマーをセットして」等、たくさんあります。また、アレクサの優れている所はオリジナルスキル(ソフト)の開発が簡単に出来ることです。
やさい塾では三つのアレクサ利用を考えました。一つ目はダンボールコンポストの講座終了後にやってもらうクイズ形式の問題(スキル)を作成しました。この問題(スキル)によりコンポストのノウハウをやさしく解説して学べるようにしています。
そして二つ目は野菜作りのノウハウ「スイカの空中栽培」「1本苗キュウリの100本採り」「トマトの年内採り」「栽培カレンダー」等のスキルを作成しておき、スマホ(アレクサ)より、いつでも、何処でも情報を聞けるようにしておけるシステムです。
やさい塾では「100才までやれる家庭菜園」を目指していますので、三つ目は認知症予防にアレクサを利用することです。例えば右脳に刺激を与える「アタック25クイズ」、眠りの質を高めるために「睡眠をサポートする音」、人との会話を補うため「アレクサとの会話」、脳をリラックスさせるために「癒しの音楽を聞く」等です。やさい塾のオリジナルスキルは講座生・塾生にメールで送信でき、やさい塾のグループ内で使えます。
<コンポスト活動>
基材開発について、半径2km以内で調達できる基材として「もみ殻」と「ワラ」の使用でダンボールコンポストが継続的にやれること、また、野菜作りの堆肥としての機能も問題ないことを確認しました。具体的には、もみ殻20Lと切りワラ(5cm以下)5Lをダンボールに入れて行います。尚、冬場(12月~3月)は気温が下がり処理能力が落ちるため、毎日、米ぬかを一握りづつ加えれば問題なくコンポストは可能です。
もみ殻クン炭をもみ殻に変えた理由はクン炭を製造時に排出される多量の煙PM2.5や有害物質で大気環境や作業者の人体に良くないからです。また井原市のコメ農家さんはもみ殻の処分に困っている方が多いこともあります。ワラの入手が難しい方は陸稲(もち米)10m2を家庭菜園に植えれば、ワラの自給もできます。
ダンボールコンポスト講座について、やさい塾は本年1月6日で発足して5年になりました。講座としては「やさしい家庭菜園講座」「家庭菜園の有機栽培教室」「出前講座」等があります。これらの野菜作り講座の中でダンボールコンポスト(生ゴミ堆肥)の作り方を教えています。
過去5年間で約500人の受講があり、そのうち、ダンボールコンポスト実施者は約200名(40%)です。更に3年以上続けている人は約50名(10%)となっています。継続者50名の方の殆どが、野菜作りに有機肥料として使用されています。「生ゴミ堆肥が美味しい野菜をつくる」と分かれば継続に繋がることだと考えられます。
<今後に向けて>
やさい塾は「100才でもできる家庭菜園」を目指していますので、健康寿命を100才に置き、その為にはどうすればよいか考えていきます。菜園➡生ゴミ堆肥・ボカシ➡野菜作り➡生きがい ➡味噌・豆腐・納豆づくり・そば打ち等を楽しみながらの活動を実践して、「やさい塾モデル」を普及させていき、健康長寿地域の実現に寄与していきたいと考えています。
1.第一回イネ・大豆育て方コンテスト」実施へ
本年度は「第一回イネ・大豆育て方コンテスト」を企画・実施しました。目的は小学生やその親御さんに生ごみ堆肥で作物が育つことや収穫した作物の加工をする体験をしてもらうことで、楽しみながら学んで頂くためです。陸稲の種籾10粒から、何粒に増やせるか、大豆10粒から何グラムとれたかを競います。ワラを使って納豆づくりを行うため、無農薬栽培が条件です。肥料のない人には生ごみ堆肥とボカシ肥を推奨し提供しました。自ら創意工夫して米と大豆づくりを学びます。そして採れた無農薬ワラと大豆から納豆づくりや豆腐づくりに挑戦し日本古来の技術を学んでもらいます。今回は25名の参加でした。イネの部の優勝者は種籾10粒から93gの収穫量で3910粒(換算値)でした。さらに収穫したワラと大豆で納豆づくりと豆腐作りにも挑戦してもらいました。自家製の豆腐は大豆の風味があり本当に美味しく大好評でした。来期もコンテストを実施予定です。
2.全国小学生作文コンクール2018優秀賞受賞
そして嬉しいニュースがありました。「やさしい家庭菜園講座」講座生のお孫さんが、おばあちゃんのやっているダンボールコンポスト(生ごみを堆肥化)に興味を持ち、夏休みの自由研究に挑戦しました。そして、その体験を基に「住みよい地球」全国小学生作文コンクール2018に応募して高学年の部で見事に優秀賞(7名/4000作品)を受賞されました。作品を読ませてもらいましたが、おばあさんからお孫さんへの環境のお話など愛情も分かる素晴らしい作品でした。この作品を通して、生ごみ堆肥のダンボールコンポストが「住みよい地球」に役立っていることを全国の多くの小学生やその関係者へPRできたと思います。我々のコンポスト活動が、社会のためになっていることが実感でき、今後の活動に元気をもらいました。
3.SOFIX技術の習得
新情報の習得ではSOFIXの技術研究会へ出席しました。9月にはSOFIX技術を実践する圃場の「健一自然農園」茶園を見学しました。茶摘みは一度だけ行う栽培法で収量を求めなければ、肥料なくても茶葉はできることを知りました。また化学肥料使用茶園の耕作放棄地をSOFIX分析して、自然農法茶園へ変えていく手法に利用していました。やさい塾でも家庭菜園への展開を模索していきます。八朔の木へSOFIX技術を応用する試験栽培を開始しました。収量UP、木の生育状況をみて効果が確認できたら土壌の変化をSOFIX分析で確認しようと考えています。
4.やさい塾年間行事の確立
やさい塾の年間行事がほぼ、確立してきて、無理なく自然に活動ができるようになってきました。
[やさい塾の主な行事]
① 2月ふれあいセンター祭りPR展示会 ②2月年間講座開講式 ③4月神辺出前講座④6月環境フェアPR展示会(イネ・大豆育て方コンテスト募集) ⑤7月市の栄養士さん指導の料理実習 ⑥8月つどえーるPR展示会 ⑦9月外部講師を招き講演会
また、今年の講座の受講生には87歳のおじいさんもいて、元気に一年間受講して頂き、修了証をお渡しすることができました。このおじいさんは毎日、自転車に乗って活動されていて、見た目には60歳代です。やさい塾は100歳でもできる家庭菜園を目指して活動していますので、我々の先輩としてお手本にさせていただいています。
5.健康長寿地域の実現に向けて
会員皆さんの好奇心(作りたい野菜、加工品等)の実現に向けて支援していけるような活動を続けることで、個人の「生きがい」につながっていきます。この「生きがい」を持つことで元気なお年寄り増えていくことが、やさい塾の活動を通して、実感できるようになってきました。
2017年度 活動状況
本年度は家庭菜園でできる陸稲(餅米)栽培をやさい塾会員へ展開しました。 目的は3つあります。
一つ目は野菜の連作障害防止です。同じ菜園に野菜ばっかり植えると、どうしても連作障害が起きやすくなります。間作に陸稲の穀物類を植えることにより、土壌菌の種類が変わり、連作障害防止につながります。
二つ目は、陸稲を10m2(約3坪)程度植えると、ダンボールコンポスト1年分(4回分)の藁が調達でき、基材の菜園内循環が可能になります。この藁で生ゴミ堆肥化が問題なく可能か?会員の皆さんに検討してもらった結果、藁の場合は、冬場の温度管理(米ぬかや天ぷら廃油の添加)が必要なことが分かりました。ヤシ殻チップで上手く実施できる人は、藁でもできることも分かりました。今後は初心者にはヤシ殻チップで実施してもらい、熟練者には藁への展開を考えていきます。
さらに野菜の間作として大豆栽培の検討を行いました。大豆を10m2(約3坪)に植え付けると約2kg収穫できます。この自家製オーガニック大豆で味噌作りに挑戦してみました。その結果、約12kgの美味しい味噌が比較的簡単に作れることが分かりました。今後は大豆を加工する豆腐、醤油づくりへの展開を考えていきます。
今年から100才でもやれる「持続可能な家庭菜園」と言うテーマで野菜作りを検討しています。菜園の広さ1アール(約30坪)、1世帯3人家族を標準とします。肥料は家庭からでる生ゴミで作る堆肥年間20kg、ボカシ肥30kgで殆ど賄えます。ボカシ肥の主成分は米ぬかです。1世帯で玄米を年間200kg購入し、精米すると20kg分の米ぬかを確保でき、30kgのボカシ肥が作れます。家庭用の精米機でも米ぬかは回収できます。畝作りには耕運機は使用しません。畝は固定畝で行い、クワで軽く耕す程度で野菜が作れる菜園を目指します。
健康長寿には生きがいと食と運動が重要です。「生きがいづくり」は家族に感謝されるような野菜作りを工夫・仕掛けづくりをします。食としては「旬の野菜の効果的な食べ方等」で野菜ソムリエ・管理栄養士さんの講座開催を計画します。運動としては、水やりはジョーロで行い、畝はクワで耕すなどを実践し、1日の作業時間・運動量を把握していきます。
100才でやれる「持続可能な家庭菜園」のすべての作業を、誰でも簡単にやれるように、標準化(マニュアル化)し、実践・検証して普及を図りたいと考えています。
やさい塾は高齢化社会での生きがいづくりを目指しています。楽しい家庭菜園を通して家族に感謝され、生きがいも感じられる、健康で元気なお年寄りが増えて欲しいと考えています。
2016年度 活動状況
1.「やさしい家庭菜園講座」の開講
これまで蓄積した堆肥、野菜作りのノウハウを広く発信していくため「家庭菜園講座 定員30名」を開講しました。ほぼ計画通りの行事ができ、皆さんからは「役に立った」「楽しかった」と高評価が得られ、来年度も引続き講座開講を継続していきます。
2.ダンボールコンポスト基材の検討
ダンボールコンポストの基材として現在、ヤシ殼チップ(インドネシアからの輸入品)を使用していますが、輸入品であり輸送により化石燃料が使われています。環境にやさしい基材をできるだけ地域内、家庭菜園内で調達できないか、ダンボールコンポストの基材試験を行いました。
その結果、稲藁で代替できることが分かりました。藁は陸稲の試験栽培の結果、1m×10mの畝で栽培すると12束 の藁が回収できます。これはダンボールコンポスト年間4回分の基材として使用できることが分かりました。来年度は会員全員に今年収穫した籾を種籾として分配して陸稲栽培を展開します。自分の藁は自給するようにしていきます。ダンボールコンポスト初心者の人及び
、藁の調達ができない人はヤシ殼チップで引続き行います。
3.餅米の一貫生産・消費
餅米・モチつきまでの作業工程は、子供の頃に見た懐かしいもので、「収穫した稲をハゼに掛け乾燥、足踏み脱穀機で脱穀し、トウミで籾を回収。籾を精米機で餅米へ。餅米を餅つき器でモチにし、雑煮にして美味しく食べる」ことまで、餅米の一貫生産・消費する貴重な体験ができました。
4.家庭菜園野菜の硝酸塩濃度測定結果
有機栽培であっても硝酸塩の高い値の野菜ができることが判明しました。3000ppmを越えるものは要注意で、一般的に葉物野菜の方が硝酸塩濃度は高く、根菜類は低いと言う文献がありますが、根菜類のダイコンは、かなり高濃度になる事が判明しました。
ダイコンは部位により濃度差があり、尻尾部及び葉が高濃度になる傾向にあります。現時点の結論としては、家庭菜園のダイコンの葉・茎には10,000ppmを超える物があり、食べない方が良いと思います。同じ根菜類でもニンジンは低く、殆どが1000ppm以下で問題ないと思います。
来年度は、野菜の種類、菜園の件数、測定件数を増やし、分析精度を上げます。更に肥料量と硝酸塩の関係等を把握して 、硝酸塩を下げる方法を検討します。
5.やさい塾 LINE運用
やさい塾の会員同士でタイムリーな情報の共有化を目的に、道の駅の珍しい野菜、野菜の育て方、野菜の病気、困っていること、美味しい野菜の料理法等をLINEにUPしています。皆さん初めてのLINEで大変苦労しましたが、何とか使いこなしています。
6.活動イメージ図の作成
「循環型家庭菜園」を少し分かり易く「持続可能な家庭菜園」と名称を改め、コンセプトの表現を修正しました。又、NHKスペシャル健康長寿の番組で、生きがい型満足感は健康長寿につながることが、科学的根拠をもとに報告されました。
我々の目指す「野菜作りを通しての生きがいづくり」は、人や家族に感謝されるので、まさに生きがい型満足感が得られます。この情報で我々の方向性は間違っていないことが分かり、「健康長寿な地域の実現」がやさい塾の最終目標になります。又、生きがい型満足感を使った活動イメージ図で表現し目標を明確化しました。
2015年度 活動状況
やさい塾では自給有機肥料を使用して、安心・安全で環境にやさしい野菜作りを目指しています。自給有機肥料としてはダンボールコンポストの生ゴミ堆肥 20kg/年と米ぬかベースのボカシ肥 30kg/年と1アール(30坪)家庭菜園から得られる植物性堆肥 20kg/年の3種類です。2012年9月から約3年間、これらの肥料だけで、1世帯分の野菜を自給する検証テストをモデル菜園で行っています。収獲量はまずまずなのですが、現状では経験と勘による施肥量であるため、本当にこれで良 いのか分かっていませんでした。そこで今回、土の中で微生物の働きが分かるSOFIX(土壌肥沃度指標)による土の健康診断を行ってみました。その結果、一部不足成分がありましたが総細菌数は推奨値6億個/g以上と比べ、8億個/gと十分に微生物量を保有していることが判明しました。総合評価でもまずまずの成績でした。又、生ゴミ堆肥・ボカシ肥もバランスのとれた非常に良い堆肥との評価になりました。
今後は、この科学的なデータを基に、誰でも簡単に循環型家庭菜園が可能になるようにしたいと考えています。又、「やさしい家庭菜園講座」の中で、ダンボールコンポストの生ゴミ堆肥、簡単なボカシ肥のつくり方等を指導して普及を図っていきます。
近年、問題視されている葉物野菜中の硝酸塩濃度について、やさい塾で各菜園の野菜を実測した結果、概ね良好な値でしたが、中にはかなり高濃度になる条件も判明してきています。今後は更に分析件数を増やし、実態把握の精度を上げて行きます。合わせて硝酸塩濃度を低減する栽培条件の検討・研究も行ない更に安全性の高い野菜作りを目指していきます。
循環型家庭菜園フロー図
SOFIX(土壌肥沃度指標)診断結果
<モデル菜園>
<生ゴミ堆肥>