1512年(?)、浦上村宗の次男として三石城に生まれる。
1531年6月、父・村宗が摂津天王寺合戦で討死すると、宗景は兄・政宗とともに
父の遺骸を葬り、書写山において追善の供養を行った。
その後、兄弟は三石城から播磨の室津城にに移ったが、程なく不和になり、
宗景は家臣の大田原、日笠、服部、延原、明石、岡本などをはじめ、約100人の従者と
ともに室津城を出る(宗景は暗愚の兄・政宗に従っていては将来が危ぶまれ、早く遠ざかり
たい気分であった)。
その後、宗景ら100人は日笠村の太鼓丸城に入り、宗景はこのたび忠勤を尽くした庄屋、
庄官などを招き恩賞を与え、力量あるものは家臣として召抱えた。
その後、東備前や美作の二郡ほどは全て宗景に従い、その勢いは凄まじいものだった。
この様子を見た室津城の兄・政宗は、宗景を討伐すべく播州勢二千を持って備前に進軍し、
五十余艘の船で海上から三石城を攻めた。政宗はこの城に住んでいたこともあり、
城の構造をよく分かっていたので忽ちこれを攻め落とした。ついで備前片上に進み、
弟で富田松山城主である浦上国秀(村宗三男)を攻めた。この城もあっけなく降参し、
政宗はこの城を本陣としてその東の山々に布陣した。宗景も太鼓丸城から出陣し、片上の
葛坂を隔てて度々合戦を挑んだが、勝負はつかず、両軍は撤退した(なお、浦上政宗に
降参した富田松山城の浦上国秀だが、のち政宗の勢力が衰えると再び宗景に従った)。
1533年、宗景は太鼓丸城を改修(以後は天神山城と書きます)。
1534年、浦上重臣・島村観阿弥が、同じく浦上重臣の宇喜多能家を殺害した。
1539年、天神山城を改修(第二期工事)。
2、北からの侵略
1543年、宗景は、能家の孫である宇喜多直家を側近として召抱える。さらにこの年、播磨の
赤松晴政が、播磨にある宗景の諸城を二、三ヶ所攻めおとしたので、宗景は百田豊前、日笠
源太らを先手として播磨へ出兵し、至るところに放火し、赤松氏の城二ヶ所を落とす。
翌年、天神山城を改修する(第三期改修)。
さらにこの年、三星城主で浦上配下である後藤勝基から、出雲の尼子国久が近いうちに
美作へ侵攻してくるので、急いで加勢の軍勢を寄越されるよう、宗景に求めてきた。
この要請に応え宗景が出陣しようとすると、今度は播磨に放っていた忍びから、赤松晴政が
宗景留守中に備前に侵攻するとの報が入ってきた。この報を聞いた宗景は美作へ後詰の
軍勢を送ることが出来ず、赤松氏の侵攻に備えて百々田豊前に三石城を守らせた。
その間に尼子国久は美作へ乱入し、浦上氏に従っていた美作の土豪、小瀬・今村・竹内・
江原・大河原・草刈・市・玉串・蘆田・牧・三浦・福田らを降参させた。しかし、三星城の後藤
勝基のみは最後まで尼子に降らなかった。なお、赤松氏は宗景が守りを固めたので、ついに
軍勢を動かすことはしなかった。
1545年、砥石山城の浮田大和が備中勢に内通しているとして、宗景は宇喜多直家に浮田大和
の討伐を命じた。宇喜多直家はこれを難なく落とし、この恩賞として奈良部城を預けられた。
なお、砥石山城は島村観阿弥の城・高取山城の並びの城であるとして、これを観阿弥に預けた。
〜美作勝山合戦〜
1553年3月、出雲の尼子晴久が近国の兵を集め、2万8千の大軍で美作の浦上領に侵攻した。
この大軍をまえに、美作の豪族は戦わずして降伏する者が多かった。
このことが天神山城に伝わると、浦上宗景は備前・美作の兵1万5千を集めて天神山城を出発
した。浦上軍は美作国高田表に本陣を設け、その近くの諸城に兵を補充し、暫く対陣し数度に
渡って足軽による小競り合いを繰り返した。
5月12日、尼子軍3千が高田の村に討って出てきたので、浦上軍は後藤勝基など美作勢2千で
これを迎撃した。やがて浦上軍美作勢の敗色が目立ってきたため、浦上軍播磨勢7百余騎が
尼子軍の横合いに攻めこみ、これを突き崩した。しかし、後詰めに控えていた尼子軍2千7百
余騎が崩れる味方を助けるため、浦上軍播磨勢に討ってかかってきた。
この形成を見た宗景は、備前勢1千5百を援軍として向かわせ、先陣を助けて攻め戦った。
こうして両軍入り乱れて戦ったが勝負がつかず、やがて日暮れになったので互いに兵を
引き揚げ、再び睨みあって対陣した。
5月22日、尼子軍は5百騎が先陣となり、さらに1千騎がニ陣に備え、宗景の先陣に対して撃って
かかってきた。これに対し浦上軍は、小寺など播磨勢3千騎が備えを進めて戦った。しかし、
序々に浦上軍は不利になり、散り散りになって引き退いた。これを見た浦上軍美作勢2千騎は、
「見苦しい戦さの仕方をするものだ」と怒って、これに入れ替わって戦った。
これに対し尼子軍も1千騎の部隊を投入したから、浦上軍も播磨勢5千騎を投入。
これを見て尼子軍もまた、尼子紀伊守ら1万騎ばかりで攻めかかったから、大軍が入り混じって
乱戦となった。両軍は午後2時頃まで戦ったが、浦上軍は多勢に無勢で尼子軍に敗れ、
前後一つになって敗走した。
しかし、浦上宗景の旗本5千騎は無傷で、これを観望していた。
これを見た浦上賢能斎という老人が、この軍勢を持って先陣を救援せよと進言したが、
宗景は、「自分の軍勢をもって乱戦の敵を追い討ちすれば、これを打ち崩すは容易い事だが、
しかし自分の備えを乱せば、尼子晴久がその旗本をもって攻めかかってくるであろう。その時
誰がわが旗本勢を助けるであろうか。そうなれば味方は総崩れになり生き残るものも稀で
あろう。旗本さえ堅固に備えておれば、たとえ先手は敗れても、総崩れになることはない」
といってその進言を退けた。
結局、浦上軍の先陣は打ち負け、討ち取られた首級は750。討ち取った首級は330だった。
その後、美作の諸城を尼子軍に攻略され、さらに尼子軍は播磨まで兵を進め、敵城17ヶ所を
攻め落とした。
しかし尼子軍の帰陣後、宗景は美作へ兵を進め、攻め取られた諸城を奪回する。
3、直家の活躍
美作勝山合戦後、備前や東美作の豪族は浦上氏に従うようになり、さらに播磨の浦上政宗や
赤松晴政の勢力も衰えたため、浦上宗景は得意の絶頂にあった。
しかし、家臣の島村観阿弥や中山備中が成羽城主の三村氏に内通しているとの噂があり、
これを確かめたところ真実であったため、宗景は直家にこれらの討伐を命じた。
直家は、島村観阿弥の砥石城も中山備中の沼城も堅城であったため、謀略をもって両者を
暗殺した。宗景はこの褒美として、島村氏の領土の大半と中山氏の沼の亀山城を直家に預けた。
直家はさらに1561年、松田氏配下で龍の口城主の撮所元常を謀殺し、さらに長年浦上氏と
敵対していた松田氏と和睦し、浦上傘下に入れた。このとき直家は2人の娘がいたのだが、
1人を松田氏に嫁がせ、1人を同じ浦上家臣の後藤勝基に嫁がせた。
1565年、備中の三村氏がその後藤勝基の居城・三星城を攻めたため、直家は宗景の命令に
より三星城の救援に向かった。直家はこの救援に見事成功し、宗景は直家配下で活躍の
あった馬場次郎四郎に感状を出した。
1566年、再び美作に侵攻してきた三村家親を暗殺し、さらに家親のあとを継いだ三村元親が
2万の大軍で備前に侵攻してきたため、直家は5千の軍勢で迎え撃ち、これに大勝した。
1568年には、婚姻関係にあった備前の有力者・松田氏を滅ぼし、西備前から備中の一部を
支配する勢力にまで成長した。
こうして直家の勢力は主家・浦上氏を凌ぐようになり、また対立も生まれた。
4、浦上政宗系浦上氏の滅亡
直家がこのように活躍しているしている中、浦上氏はというと、1564年に浦上政宗の嫡子・
清宗と黒田職隆の娘が婚姻しようとしたところへ、龍野城主の赤松政秀の軍勢が襲いかかり、
政宗・清宗父子は討死した。しかし黒田職隆の娘は辛くもこの難を逃れ、後に、浦上政宗の
次男である誠宗に嫁いだ。この夫妻は男子を1人生み、久松丸といった。
一方、天神山城の浦上宗景はこの状況を見て、浦上政宗系の浦上氏を滅ぼす好機だと思い、
浦上誠宗配下の江見河原源五郎という者に浦上誠宗暗殺を依頼した。
密命を受けた源五郎は、1567年5月18日の深夜に誠宗の居城に侵入し、これを殺害した。
しかし誠宗の子・久松丸は難を逃れ、小塩というところに移った。【つづく】
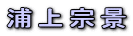
1、兄弟分裂