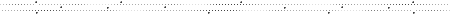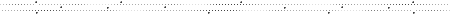Nightmare
夜が鳴いている。
弧を描きつ円を描きつ、蝙蝠が夜空に華麗な舞を披露していた。
刃の形をした月は昏い影を地面に落とし、夜に蠢く生物達の視界を開く。
だが、何時もなら狭い裏路地にたむろする鼠達は、今夜に限って残飯を漁ろうとしない。
「…ぁ…ぁ…」
仰け反った白い喉に、また青白い月の光が落ちた。
最早悲鳴すら上げられぬ少女に覆い被さり、その甘美な味に一人の男が酔い痴れている。
灰色のインバネスを纏い、整った容貌を持つ男がうら若い乙女の首筋に顔を埋める光景は酷く扇情的だった。
時折零れる荒い吐息は、何処か差し迫った物を感じさせない事も無い。
「あら…残念だわ、その娘は私好みだったのに」
軽やか、その上に艶やかな声が男の背後から突如響いた。瞬間、風を裂いて娘の喉元に突きつけられたのは男の拳、
否、その指先から伸びた忌まわしい光を放つ鍵爪である。
「…厭だ、何をそんなに警戒しているの?」
しかし娘の艶めいた声は1ヘルツも揺らぐ事はなかった。
それどころか、その白い顔には微笑すら貼り付いている。
まだ肌寒い時期だと言うのに、しなやかな肢体に纏われた漆黒のドレスは彼女が持つ色香を存分に増長させていた。
僅かな幼さをその美貌に残していながら、悩ましげな曲線を描く胸元。
にい、と三日月を形取った唇の隙間から、鋭い輝きが零れる。
「何だ…長生種どうぞくじゃねぇか…」
「何?教皇庁ヴァチカンとでも思ったの?」
「まさか」
唇の端から一筋の血と鋭い輝きを覗かせてせせら笑う男との、軽い言葉の応酬。
やっと下ろされた男の腕を認め、娘は肩を竦めて笑った。
そして組んだ腕をゆったりと解くと、男の元へと一歩歩み寄る。
青白い月光は、彼女を彼岸の者の如く照らし出した。
「あ?分けて欲しいってか?」
「そうね、お礼には私なんて如何かしら?」
「そりゃあまた…露骨な誘い方だな」
粘着質で好色な視線を向けられた娘は、依然妖しく微笑んでいる。
つう、と男の骨張った指が白い顎を辿った。
「このまま此処でってのも結構ソソられるな…どうだ?」
「厭よ、こんな汚い所」
口先では嫌がりつつも、滑らかな動作で娘の白い繊手が男の骨張った手を取り、自らの腰へと導く。
男も遠慮する事無く、進んで娘の形良い曲線を撫でた時だった。
「 ヘンスヒェン・フォン・ツェルプスト、父と子と聖霊の御名の下に貴方を二十四件の強姦・殺人及び
血液強奪容疑で逮捕します。私は教皇庁国務聖省特務分室Axの派遣執行官、・…。
警告します、速やかに投降して下さい」
死に値する宣告に男が色を失くすのと、娘が太腿に隠していたオートマチック・リボルバーを引き抜き男に突き付けるのと。
一体どちらが速かっただろうか、鈍い音を立て、冷汗が伝う男のこめかみと冷たい銃口が擦れ合う。
先程までふんだんに媚を含んでいた娘の態度は跡形もなく掻き消え、代わりに冷え切った双眸が男を射抜いていた。
だが、窮地に在りながらも男…吸血鬼ヴァンパイアヘンスヒェン・フォン・ツェルプストは教皇庁の派遣執行官を嘲弄する。
「ケッ…長生種どうぞくのくせにヴァチカンのイヌにまで成り下がったか…」
「長生種どうぞく?貴方みたいな卑屈な人に連帯感を持たれるのは謹んで辞退するわ」
穏やかに切り返されつつも同時に骨の髄まで侮辱した言葉は、ヘンスヒェンの激昂に火を点けるには十分過ぎた。
「 舐めるなよ、イヌ!!!」
音速に近い動きで繰り出された蹴りが、の細い顎を掠める。
コンマ単位の差で尼僧が飛び退いていなければ、彼女の頭蓋は顎から粉々に砕かれていただろう。
そのまま反動を利用し信じ難い跳躍力で夜空に舞った細い影は、瞬きをする暇も無く地上の吸血鬼に向かい発砲する。
静かな夜に、三つの消音機サイレンサーの音が響いた。
「…残念だったなぁ?あ?」
「!」
だが、軽やかに地に足を着けたの背後から響いたのは下卑た嘲笑だった。
軽く焦燥に駆られた瞳を尼僧が向けた瞬間には、既に重々しい音を立てて拳銃は砂埃に塗れている。
長生種メトセラの驚異的な力で砕かれたのだろう、奇妙な方向に捩れた手首を見遣っては嘆かわしげに首を振った。
「もう…ここまで砕かれたら治るまで結構な時間が掛かるじゃない」
「 テメェ、自分の状況が判っててホザいてんのか?」
尼僧の手から拳銃を叩き落し、尚且つその白い喉に鋭い爪を這わす男の声はこの上なく怒りを孕んでいた。
の声がこの場にそぐわぬ間延びした物である事も、男の激昂を煽るだけである。
「派遣執行官様とやらが口ほどにもねェな」
こめかみに青筋を浮かせながらつう、とヘンスヒェンの鉤爪の切っ先がの喉笛を滑った。
それでも尼僧は怯える事も抵抗する事も無く、只静かに吸血鬼の行動に身を任せている。
これが如何に彼女にとって不利で生命の危険さえ色濃い状況だと言う事を、本人は知っているのだろうか。
だが男が幾等罵倒しようと嘲弄しようと、その白い顔は打って変わって仮面の如く何の感情も見せなかった。
「…いい加減にしろよ、オイ」
「あら、何をそんなに怒っているのか皆目見当つかないわ」
そのくせ、平気な顔してその雄弁さを以て火に油を注ぐ。
そんな彼女に、散々侮辱されたヘンスヒェンの怒りが最高潮に達するのは時間の問題だった。
今までは只滑らせるだけだった鉤爪を、遂に咆哮と共に滑らかな肌に喰い込ませる。
「 フザけんのも大概にしろ!!!殺す…絶対ェ殺すこのアマ!!!!!!」
完全に自分を嘗め切った態度、それが吸血鬼にはどうしても許せなかった。
ましてや、己と同じ種族でありながら、天敵である教皇庁に加担しているなどと!
ヘンスヒェンが同族の喉首を半分握り潰したその時だった。
今まで微動だにしなかった尼僧が、不意に男を振り返る。
命乞いか?吸血鬼は直感的に、そう、思った。
だが、娘の表情は男が想像したそのどれもとは異なっていた。
昏い三日月と捩れた紅い月の下、白い肌を鮮血に染めた天使は穏やかな微笑みを浮かべていた。
「 残念だけれど、一つ訂正があるの」
微笑みに反し潰れた声で尼僧が喋り終えるか終えないかの内に、突如として男の眼前の闇が切り裂かれる。
暗く濡れた闇の隙間から、細く赤い光が地を這いやがてはヘンスヒェンの身体を這い登った。
既に吸血鬼は、尼僧の喉笛を握り潰す事などとうの昔に忘れ去り恐怖に目を見開いている。
人間の視力では姿こそ明瞭に見えなかったが、恐慌しきった吸血鬼の視線の先には確かに何者かが居た。
そんな男の怯えきった様子を、娘は実に酷薄に楽しげな様子で見つめる。
「私は よ」
やがて朱に染まった天使は、その朱よりももっと紅い唇で吸血鬼に死を宣告した。
何かおぞましい物でも見たかの様に、目を見開き身体を戦慄かせる男に。
「 ご機嫌よう」
断末魔の木霊を最後に、裏路地は死んだ様に静まり返った。
Ⅱ