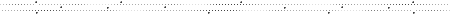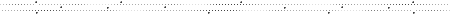どうして昨日の内にでも家を出ておかなかったのか。
後悔先に立たずとは良く云った物だ。
序章―春― 薔薇と十字の洗礼
『 榎木津ゥ?』
思わず妙なイントネイションで喋ってしまった。
きっととんでもなく間の抜けた表情をしていたのだろう、父がからからと嗤う。
『何て 言ったの、今』
『だから榎木津礼二郎君の所にお嫁に行きなさい、と言っただろう』
私の質問に、父は至極丁寧に纏めた言葉を返してくれた。
彼ならお前も構わないだろう、と付け加えるのも忘れていない。
私はと言えば、死刑の宣告をされた犯罪者の様に顔色蒼白となっていた。
例え明日から日本が亜米利加領になると聞いても、絶対に此れ程までには驚くまい。
『ね、ねえお父様』
『何だ』
『前言撤回 は、駄目?』
『当たり前だ』
目の前がいよいよ真ッ暗になった。
『何をそんなに嫌がっとるんだ。礼二郎君とは昔から付き合いが有るじゃあないか』
いや、そんな履歴はむしろ抹消して欲しい。
もっと希望して良いのなら、最初から他人同士だったと言う事にして欲しい。
そう。
私は榎木津礼二郎が嫌いだ。
理由は至極明快である。
彼が私にとって量り切れない人間で有る事。
彼が昔から兎に角女の子が好きであると云う事。
彼が自分の行動がどれだけ人に迷惑を掛けているのかを理解していない事。
ざっと挙げてみれば此の様な具合だ。
しかし、私が今どんなに抗議した所で受け入れて貰える筈も無く。
現在、車の後部座席で荷物を抱えて居るのだった。
「 ねえ、鈴木さん」
「何ですか御嬢様」
「此の侭私を連れて何処かに逃げてくれない」
ちんまりと座って先程の言葉を呟けば、直後、盛大に我が家の運転手は噎せた。
序でに云えばハンドルの切り方を間違えたらしく、車体が左右に揺れる。
やがて咳が治まり揺れも収まると、鈴木さんはバックミラア越しに私をめっと叱った。
「突然妙な事を仰らないで下さい」
「あら厭だ、一寸ばかし本気だったのよ」
「一寸ですか」
ハアと今年二十九になるお抱え運転手は溜息を吐く。
彼、鈴木敬之助が我が家に来て働き始めたのは丁度十年前だ。
そして運転手業の傍ら幼かった私の守り役も勤めてくれていた。
勿論迷惑も山程掛けている という訳で、本日も彼は私の守り役にされたのだろう。
否、押し付けられたとでも云うべきか。
そして何時も通りの安全運転に戻しつつ、鈴木さんはぽつりと呟いた。
ささやかな爆弾 きっと先刻の仕返しだろう を込めて。
「でもまあ、あれですね」
「何が」
「榎木津様へのお嬢様の態度の変わり振りが不思議だって事ですよ」
「 なっ」
飛び出して来た、思いも寄らない言葉に私は絶句した。
しかし二の句が継げないで居る私を其の侭に、鈴木さんは言葉を続ける。
「昔は礼ちゃん礼ちゃんと善ッく懐いていらっしゃったのに 」
「いや、一寸鈴木さん」
「榎木津様が復員されて目を傷められていると分かった時なんか、もう大騒ぎで」
「鈴木さんッ」
半ば叫ぶ様に諌めると、やっと鈴木さんは黙った。
しかし、バックミラア越しに見える其の口元が吊り上っていたのは、決して気の所為では無いだろう。
何時も困らせに困らせている竹箆返しか、私の守りを押し付けられた腹いせか。
「其れが小学校を卒業される頃には、もう榎木津様を厭がる事甚だしくなって仕舞われて」
「だから何でそんな事を今頃 」
「でもこうしてお嫁に行かれると云うのは ハア、運命とやらでしょうかね」
「厭だ、間違ってもそんな事云わないで頂戴。寒気がするわ」
「やあ、なんて酷い仰り様だ」
ケッコンケッコンと芝居がかった口調で、鈴木さんは私の不快感をどんどんと煽って行く。
ケッコンだかコケコッコーだか良く分からないが、もうどっちでも構わなくなって来た。
それに良く考えれば、今から嫁入りする訳では無いのだから今までのは杞憂に過ぎなかったのだ。
私は僅かな苛立ちと多大な安堵感を込め、運転手に反論する。
「其れにまだ結婚と決まっては無いわ、会いに行くだけじゃない」
「 あ、ああ、そうでしたね」
「そうよ上手い事行けば、断れるかもしれないの 鈴木さん、如何かした」
ほんの少し、少しの間。
しかし、鈴木さんの返答に空いた其れが厭に気になって私は妙に思った。
気の所為か、と思うにはあまりにも不確かだったのである。
其の疑問を解消すべく私は声を掛けたが。
「ねえ、鈴木さん様子が変じゃ 」
「お嬢様、着きましたよ」
唐突に遮られる言葉。
私が眉を顰め不快を顕わにしても、鈴木さんは無視して車を降りドアを開ける。
だが、元々溜まりに溜まっていた私の鬱憤も限界にまで達していた。
そもそも我慢を重ね此処まで来ていると云うのに、何故喜ばしい事と云われなくてはならないのか。
私は頑として座席から動かなかった。
「私は車で待ってますので、いってらっしゃいませ」
「矢ッ張り厭よ」
「 行って頂かないと私が旦那様に怒られるんですッ」
「ちょっと私の人生とあの五十路の命令とどっちが大事なのッ」
「………………」
今にも泣き出さんばかりの鈴木敬之助、二十九歳との口喧嘩。
何やら情けなくてこっちまで泣きたい気分だ。
彼が口を噤んでしまったのは、矢ッ張りどちらに転んでも彼の人生が危ういからであろう。
「 お願いですから行って下さいッ」
「私に死ねと云うの!」
「そんな大袈裟な!」
遂に鈴木さんは私を車から引っ張り出し、ビルヂングの入り口まで引き摺って行った。
抵抗を試みるも、悲しいかな、男女の力の差と云う奴で敵いもしない。
人攫いとでも叫んでやろうかとも思ったが、彼の名誉の為に止めて置いた。
はっと気が付けば傍には『榎木津ビルヂング』と彫られたプレート。
榎木津、と言う事は此処は榎木津礼二郎の居住地なのだろうか。
いや、そもそも目的地はあいつの居住地なのだから、疑問形では無く断定形にすべきなのだ。
やがて硬直していた私の耳に、会話が飛び込んで来た。
「嗚呼、お久し振りです榎木津様」
「小父さんは口髭を生やしたんだなッ」
「お迎えにまで出て下さって恐縮です」
「馬鹿親父が煩かったからね」
「話し合いの通りお嬢様をお連れしましたので、どうぞ宜しくお願い致します」
「小父さんに口髭は似合わないよ」
一部分しか噛み合う事を知らない会話。
傍から聞いているだけで頭痛がしそうである。
しかし、私も数秒後には此の中に加わる事を強要されるのだろうか。
嗚呼、そんな事を考えるよりも、本来私は此の時点で状況を打破する術を考える必要が在ったのだ。
「ところでは何処だッ」
「ですから先程からお連れしていると申し上げているのに」
「じゃあ此れか」
此れとは何たる言い草か。
あまりにも無粋で失礼極まりない言葉。
そう思ってしまったが故に、其れが私のちっぽけな自尊心を掠ってしまったが故に。
畏怖よりも嫌悪よりも、生来の勝気さが私を上向かせた。
「本当だ。僕が視える」
鳶色した大きな硝子の眼も。
透ける様で、何時か透明になってしまうんじゃないかと思っていた肌も。
厭でも耳に残る低い声も。
屈んでくれなければ顔がよく見えなかった位高い身長も。
記憶と寸分違わぬ榎木津礼二郎が、私の顔を覗き込んでいた。
「 では、挙式までお嬢様がこちらにお世話になります」
それから、私の聞いた話とは全く以て異なる話を鈴木さんが云ったと気付いたのは。
可愛い可愛いと連呼し続ける榎木津に、硬直した侭抱き締められて数秒後の事。
参