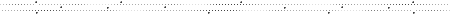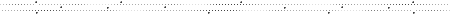「嫁に行かないか、」
「・・・・・・・・・・・・はい?」
序章―春― 受難の始まり
昭和27年、春。
つい此の前高等学校を卒業した私は。
何やら人生を大きく狂わされそうな状況に巻き込まれようとしていた。
「すみませんお父様、御年を召された所為か知りませんけど何を仰ったか意味が分かりません」
「はっはっは、娘に其処まで云われるとは儂も年かな」
「分かってるじゃないの」
此処は離れの畏まった書院造の座敷。
障子を開けた向こうに見えるのは、よく手入れされた日本庭園。
樹齢何年だろう、満開の桜の古木には鶯が留まっている。
のほほんと茶を啜った父は、自分の言葉の重大さを全く理解していないらしかった。
嫁に行く。
イクォール結婚。
結婚。
「 厭!」
芋蔓式の思考の後の叫びは、我ながら驚く程の大音量であった。
しかし当の父はと云うと、少しは年頃らしくしなさいとのたまっただけである。
私の話等ちっとも聞いてくれようとしない其の姿勢に、苛立ちが募り始めた。
「お父様、一体私が何歳だと思ってるの」
「十八だな」
ひい、ふう、みいと指を折って数えられた。
「私大学に行きたいの、働きたいの」
「大学は無理でも、働くなら結婚しても出来るだろう」
大仰に両手を広げて答えられた。
「顔も知らない相手となんて厭」
「誰がの知らない相手だなんて云ったんだ」
誰も云って無い。
開いた口が塞がらないとは正にこの事である。
終戦から七年。
一度は焦土と化したこの国だが、驚く程の速さで復興を遂げつつあった。
そんな中私の家は戦前から続く製薬会社を経営しており、そこそこ繁盛もしているらしい。
そして父も先の戦争で徴兵される事無く、現在は一家円満 に、日々を過ごしていた。
そう、つい先刻までは。
確かに時世が変わったとはいえ、まだまだ女性の立場は弱い。
学生だった頃、既に親の決めた婚約者がいる同級生もいた。
私も曲がりなりに弱小会社の令嬢 と云えば聞こえだけは良い である。
幸せな未来予想図を描けと云われても多分に無理である。
だから早く大学に入って就職して自立して、とっとと家から離れようと思っていたのだ。
なのに。
その矢先の晴天の霹靂だった。
「後生ですお父様ッ!縁談は無しにして下さい!」
「これ以外か?ほう、大した心掛けだな」
「これも含めて全部ですッ」
本来なら糞爺とでも叫んでやりたい所だが、立場が弱過ぎる。
叫んだ時点で思う壺だ。
全部か、と暢気に父は呟いて庭へと顔を向けた。
「しかしだ、。社長の儂が此れを断ったら、会社の成り行きがどうなるかは読めるだろう」
ぽつり、と悲しそうに一言。
嗚呼。
ここまで作り話めいた状況とは存在する物なのだと思い知った瞬間だった。
お家の為に泣く泣く意に添わぬ相手と結婚する若い娘。
まるで何処ぞの三文小説である。
希望も何もかも木ッ端微塵にされ妥協させられ、私も庭へと顔を向けた。
もう覇気も何も有った物では無く、取り敢えず父に尋ねてみる。
「お父様」
「何だ」
「相手は誰。 嫁に行ってあげるから、教えて」
ほう、と訳の分からない声を上げて、父がこっちを向いた。
「 そうか、行ってくれるか。明日は台風でも来るかな」
「馬鹿云ってないで答えて。羽田か柴田か織機、何処なの」
「そうか、はっはっはっはっ」
気味の悪い声で父が笑った。
何だと思わず眉間に皺が寄る。
「そんな所じゃあ無いに決まっておるだろう」
「誰だって聞いてるのよ」
苛々して、自然と声気が荒くなる。
はっきりしない父の態度にそろそろ堪忍袋の尾が切れそうだ。
かこん、と獅子脅しの間抜けな音が庭先から響いた。
直後に、はっははは、と父はもう一回笑って。
「喜びなさい、榎木津さんの所の礼二郎君だ」
爽やかなまでに、本日二回目の晴天の霹靂を落としてくれた。
弐