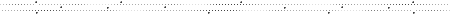「 トレス」
紅を刷いてもいないのに、酷く紅い唇は確かにそう音を刻んだ。
100:とこしえ
空は雲ひとつなく、ただひたすらに蒼かった。
白く滑らかな肌を呈する大理石。
汚れ一つないそれを覆うのは真紅の花を散らす蔓薔薇だ。
「何時から…此処にいたの」
「 記憶していない」
「嘘を吐くのはやめて」
有り得ない答えに、少女は柳眉をあからさまに顰めた。
此処は小高い丘の上。
ミラノを見渡せる 丘の上。
トレスは横たわって、静かに白い墓標を見上げていた。
確か、あの時自分に存在理由レーゾンテートルを与えた顔もこの様に白かった。
そして自分の額を静かに撫でる手も 白い。
此処には白しかない、彼は漠然と感じた。
「この彫刻レリーフ 誰が彫ってくれたのかしら」
耳朶を吐息が掠って、澄んだ声音が人工鼓膜を打つ。
「…見て、貴方がいる」
殺人人形キリングドールは答えなかった。
膝に乗せた身体は気を抜けば落としてしまいそうで怖い。
彼等の眼前に無言で聳える墓標には、一人の女性が彫られていた。
微笑む美しい顔はまさに生前そのものだ。
その右の繊手には神に仕える身であることの証の御杖。
その左の繊手には敵を打ち滅ぼす為の抜き身の剣。
しなやかな身体に纏うのは厳かな法衣。
足元には一匹の 逞しい犬が頭を垂れている。
それが、今や”ミラノの聖女”と崇められる存在となった女性 カテリーナ・スフォルツァの墓だった。
しかし、ただ其処にあるのは冷たい石の塊だけ。
あの口元に湛える上品な笑みも、けぶる睫毛に縁取られた灰色の瞳もない。
教皇に枢機卿というその身分を剥奪・追放されても尚、病を圧して世界の為に戦った美女。
そんな文句を思い出して、知らず、の口元に笑みが浮かぶ。
誰も本当の彼女を知りもせずに、よくもまあここまで好き勝手に美辞麗句を連ねた事だ。
そう、自分たち以外誰も彼女の事など知り得ないのだ 目頭が熱くなるのを少女は必死に押し留めた。
「 シスター・」
「…なあに?」
不意に零れた平淡な声に、少女は首を傾ける。
その声が酷く焦燥に駆られているような気がして、幼子に問うかの如くに聞き返した。
「俺はミラノ公に廃棄された 卿の要求を果たせ」
生きる望みを完全に絶たれた、そんな声。
纏った服はぼろぼろ、右腕は肩から千切れてしまい既にない。
あちこち傷ついた人工筋肉の隙間からは皮下循環剤が流れ出している。
血の様に赤いそれは、の纏う純白の尼僧服を夕焼けの色に染めていた。
要求 かつてあの冷たいリノリウムの床で放った言葉。
己の父母を何の躊躇いも無く殺した男への復讐。
はいつかそれを果たすことだけを考えて、カテリーナに跪いた。
だが、今は ………。
覗き込まれた、感情を映さぬ自動人形オートマタの瞳は少女に破壊される事を望んでいるように見えた。
「 分かったわ」
ブルネットの短い髪をくしゃりと掻き撫ぜ、事も無げには微笑んだ。
彼女の紅い唇が下弦の月を描いたのを認めて、トレスは安心したように静かに薄い瞼を伏せた。
「…ひとつ、これから私と一緒にアルビオンへ行きましょう。”教授プロフェッサー”に修理してもらわなくては」
だが、拳を振り上げるでもなく牙を剥くでもなく、彼の耳朶を打ったのは穏やかな声。
驚いた様に双眸を見張り、上体を起こしてこちらを見つめる男に少女は微笑んで続ける。
「ふたつ、貴方と手を繋ぎたい…皮膚を張ってもらえると尚嬉しいのだけど」
「シスター・」
トレスの諌めるような声にも、少女は応えない。
彼の残った左手を取り、剥き出しの冷たい金属をいとおしげに撫でただけだ。
「みっつ ”機械”でも”人間”でもなくて、”貴方”は私とこれから一緒に…生きてくれますか?」
左右非対称の瞳孔を持つ瞳が、真摯に硝子玉の瞳を射抜いた。
そのまま少女は強引に男の胸へと飛び込んだ。
反射的に上げた腕のやり場が見つからず、トレスはどうすることも出来なかった。
だが薄い唇は、幾時もせぬ内に非難を紡ぐ。
「 否定ネガティヴ、卿の要求は俺を破壊する事の筈だ」
「違わないわ、貴方は”いつの”要求だなんて一言も言ってないもの」
無機質な筈の声が、僅かに動揺しているように思えたのは思い過ごしだろうか。
鈴を転がすかの如く少女の声が笑った。
トレスの意見を一蹴した唇は、尚も要求を続ける。
「貴方の傍にいたい」
「………………」
「貴方に傍にいてほしい」
少女の僧帽コイフは既にずり落ち、静かな風が柔らかな髪を弄っていた。
今、血も涙もない殺人人形の硝子玉の双眸は一体何を見ているのだろうか。
「 了解ポジティヴ」
やがて背を強く抱き返してくる何かに気付いて、少女の頬を一筋の雫が伝った。
END
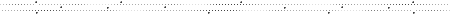
ちゃんプロポーズの巻(笑)
本当は100のお題最終話にしたかったんですが急遽変更と相成りました。
アベルはカインに勝ったものの行方不明、世界は平和にというのが私の勝手な妄想(申し訳ない)
吉田先生、こんなん書いてますが彼等の話は私の中でまだ続いています。
素敵な物語を書いて、そして遺してくださって、本当に感謝しています。ありがとうございました。