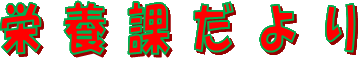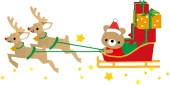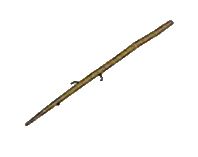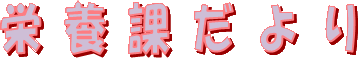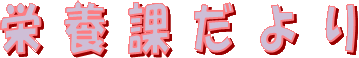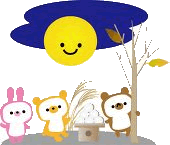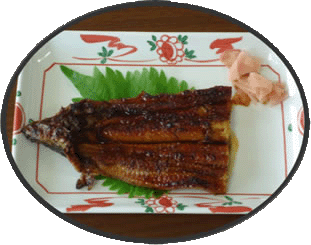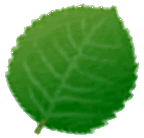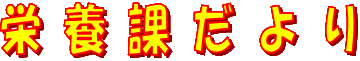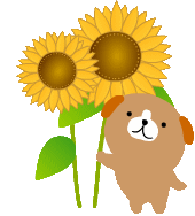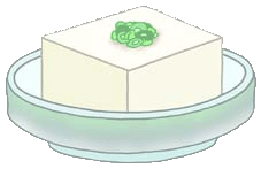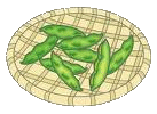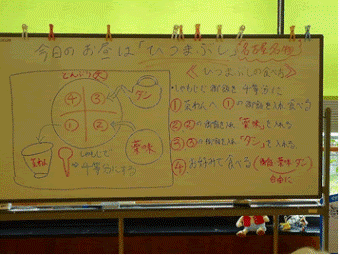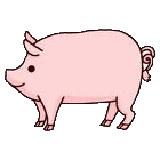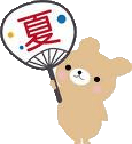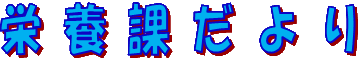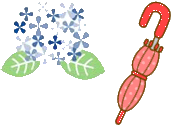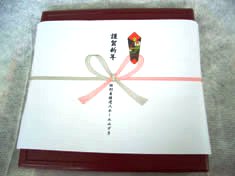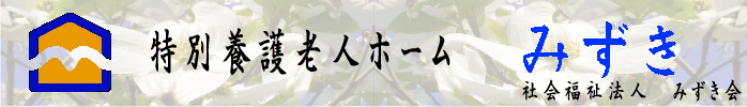 生きるってすばらしい! 『心と心・手と手・笑顔と笑顔を約束に!』 私達「みずき」はお手伝いさせていただきます。 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||
| 早いもので、もう年の瀬です。1年が経つのは本当にあっという間ですね。 | ||||
12月といえば、もうすぐ「冬至」。今年は12月22日がその日にあたります。 冬至にはかぼちゃを食べる風習が昔からありますが、これは、かぼちゃにはビタミンAやカロチンが豊富で、肌や粘膜を丈夫にし、感染症などに対する抵抗力をつけてくれるため、「冬至にかぼちゃを食べると風邪をひかない」という理由があるからのようです。
また、冬至には「ん」のつくものを食べると「運」が呼びこめるといわれ、 にんじん、だいこん、れんこん、うどん、ぎんなん、きんかん……など「ん」の つくものを「運盛り」といい、縁起をかついでいたそうです。 かぼちゃを漢字で書くと南瓜(なんきん)。つまり、「運盛り」のひとつになります。 かぼちゃの旬は、本来は夏ですが、長期保存が効き、保存中の栄養素の損失が他の野菜に比べて少ない事から、冬の時期の貴重な栄養源でもあったようです。 |
||||
|
||||
さて、12月5日〜5日間、くらしき作陽大学から実習生の方が2名来られました。 今回、実習生の方にはおやつづくりでのご協力を頂き、12/7(水)に(詳しくはおやつ作りの方で取り上げますが…)デイサービスの利用者様と一緒に、クリスマスリースをかたどった「蒸しドーナツ」を作りました。ドーナツの生地は抹茶味で、中には人参・ひじき・豆腐・スキムミルク・チーズも入っていて、なんとも栄養満点! しかもとっても美味しくできました。お二人にはご協力をありがとうございました!! |
||||
 |
||||
11月16日(水)には、特養で出張握り寿司の行事食を行いました。 もちろん、今回もいつもお世話になっております「大幸寿司さん」のご協力を頂き 美味しい握り寿司を提供する事が出来ました。利用者様の中には、1週間前から カウントダウンをするほど楽しみにされていた方もおられ、大変喜んで頂けたようです。 |
||||
 |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| 栄養課 | ||||
| TOPへ戻る |
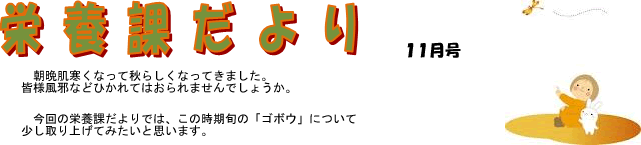 |
|||
●ゴボウの食用 ゴボウの根を食用としているのは、日本と朝鮮半島、台湾、中国北東部の一部に 限られており、ヨーロッパなどでは初夏に若葉をサラダとして食べることがあるよう ですが、根は食べません。 「戦時中、外国人捕虜にゴボウを与えたところ、木の根を食べさせられたと誤解され、 戦後にBC級戦犯として虐待の罪で処罰された」という逸話もあるくらい、国によって その食文化の違いがあるようです。 |
|||
|
|||
|
|||
●皮剥き、アク抜きはゴボウのいい所を逃がしている? 「ゴボウは皮を剥いて、切った後はアク抜きのため酢水にさらしましょう」 昔からそのように教えられてきたのではないでしょうか。 しかし、ちょっと待って下さい、ゴボウの良さは皮にこそあるといえます。 ゴボウの香りや旨みは皮のすぐ下の部分に多くあります。皮を剥いてしまうと、 せっかくの香りや旨みを捨ててしまう事になります。 また、水や酢水にさらしたゴボウからは茶色い汁が出てきますが、これはアク(不要物)ではなく、ポリフェノールという抗酸化作用(若返りに不可欠な働き)を持つ大事な 栄養素のひとつなのです。 つまり、皮剥き、アク抜きは「ゴボウの持つ大事な栄養素を捨ててしまう」皮肉な結果を招いてしまう行為になるのです。
とはいえ、お客様へのおもてなし料理では、皮を剥き、酢水につけての黒色防止 作業も、やむを得ないと思います。 でもやっぱり、家庭料理として召し上がる場合には、皮つきのままが、おいしくて 栄養素も豊富なので、ごぼうの皮はたわしや包丁の背で表面をこする程度にとどめ ましょう。 |
|||
●ゴボウの切り方 ゴボウは鍋物の具材にしたり、煮物、揚げ物、サラダ、きんぴらにするなど 色々な調理法がありますが、栄養素のリグニンは空気に触れる事で成分が増えるので、 細く薄く削るささがきは理にかなった切り方と言えます。 |
|||
●おいしいゴボウの見分け方 太すぎたり、ヒビ割れたりしたもの、葉の付け根が黒ずんでいる」ごぼうは避け、 「まっすぐ伸びて、ひげ根が少なく、肌のきれいなもの」が良いそうです。 |
|||
●ゴボウの保存方法 ゴボウは乾燥すると硬くなり、風味が落ちてしまいますので、泥つきの方が風味や鮮度が落ちにくく、洗ってあるゴボウよりも長く保存できます。 家庭での保存方法として泥つきのゴボウの場合は、洗わずにそのまま新聞紙に包んでから、風通しの良い涼しい冷暗所で保存しておくと良いです。 洗ってある「洗いごぼう」や、春先から初夏に出回る柔らかい「新ごぼう」は、泥つきのものより断然鮮度が落ちやすいので、湿度を逃さないようラップに包むか、ポリ袋などに入れて冷蔵庫の野菜室で保存し、数日の間に食べ切るようにしましょう。 旬のおいしい皮つきゴボウを食べて、身体の中からきれいになりましょう |
|||
|
|||
| TOPへ戻る |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
今回のバイキングでは、なんと、いつも出張寿司でお世話になっております 大幸寿司さんにもご協力頂きまして、従来より規模を拡大しての大イベントとなりました。 大幸寿司さん、美味しい握り寿司をありがとうございました。皆さんとっても喜んで おられました。
そしてみずきの厨房さんも腕を奮って下さいました。厨房さん、いつもありがとうございます。 机に乗り切らないほどのごちそうを目の前に、利用者様もさぞ食欲が増し、満足して頂けた事と思います。
そして、ご家族の皆様にもたくさんのご参加を頂き、ありがとうございました。 今回写真には乗せておりませんが、ご家族様には綿菓子、アイスのご協力を頂きました。 綿菓子を頬張る利用者様の笑顔を見ることが出来て、幸せな気分を少し分けて頂きました。
特養職員からは、焼きそば(写真有)・チョコレートフォンデュの参加をして頂きました。 焼きそばはソースのいい香りが漂っていて、食欲をそそりました。 チョコレートフォンデュは専用の器具がなく、鍋にチョコを入れていたので、ちょっと 雰囲気がでなかったかもしれないけど、珍しいので興味を持たれる方もいらっしゃい ました。バイキングの中にある好みのフルーツや、プチシュークリームをチョコにつけて食べると美味しかったです。
皆様のご協力のもと、無事行事を終える事が出来て、本当に良かったです。 ありがとうございました。 |
||||||||||||||||||||
9月20日(火)デイサービスで敬老会の行事食、松花堂弁当を実施しました。 |
||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||
メニューは松茸ごはん、松茸の済まし汁、お刺身盛り合わせ、天ぷら盛り合わせ、 茶碗蒸し、果物と、大変彩りよく、今の時期にピッタリのお弁当でした。 お弁当の蓋には「祝 敬老」として、手作りの熨斗をつけさせて頂きました。
そしてデイサービスでは、化繊ノズル釣りクラブさんから沢山のお魚をご提供頂き、 厨房さんが腕をふるって、9月26日(月)に豪勢なお魚料理を提供させて頂きました。 化繊ノズルさん、美味しいお魚をありがとうございました。
残念ながら料理の写真を取り損ねてしまいましたが、利用者様はやはり新鮮なお魚が お好きなんだなあと改めて感じさせられました。 特にメバルの煮付けは大好評で、すぐに売り切れてしまいました。 皆さん、とても箸が進んでおられました。 |
||||||||||||||||||||
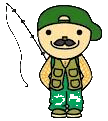 |
||||||||||||||||||||
改めまして、敬老の日を迎えられ、皆様これからもますますお元気でご活躍下さい ますよう、心からお祈り申し上げます。 |
||||||||||||||||||||
| 栄養課 | ||||||||||||||||||||
| TOPへ戻る | ||||||||||||||||||||
|
||||||
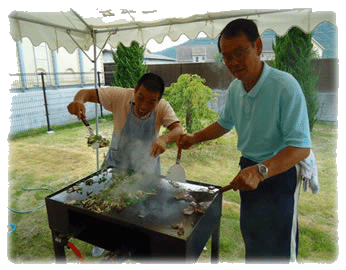 |
 |
|||||
 |
 |
|||||
写真(上)でデイサービスの職員さんに協力を仰ぎ、調理していただきました。 利用者様には焼きたてほやほやのお肉(岡山県産の牛のサーロインで、 その後、焼きそばも作り、利用者さまの大好きな果物バイキングも行いました。 利用者様はすぐにおなか一杯になられたようでしたが、目先の変わった行事食の提供と なりました。
|
||||||
|
||||||
夏バテしたこの時期に食べるのにちょうどよい果物といえます。 しかし、食べ過ぎると余ったエネルギーは脂肪として体内に蓄えられてしまうので、 注意しましょう。 また、ぶどうにはビタミン類、鉄、カリウムなどが多く含まれています。 干しぶどうにする事で、カリウムの量は増え、食物繊維や鉄も豊富なので女性に おすすめですが、糖分が多いので毎日少量ずつ摂取した方が良いでしょう。
さらに「ポリフェノール」という栄養素について耳にした事があると思いますが、 これは、ぶどうの皮に多く含まれる抗酸化物質で、色素成分「アントシアニン」の ポリフェノールは、動脈硬化の予防に役立ちますので、脂肪分の多い肉料理を 食べる際には白ワインより赤ワインを一緒に摂るのがオススメです。 |
||||||
●ぶどうの選び方 ぶどうは粒が揃っていて、皮にハリがあり、軸の太いもので、粒がポロポロ 落ちないものが新鮮です。 また、ぶどうの粒の表面についている白い粉「ブルーム」は病気や乾燥から 守るために実から出たものなので、粉がきれいについているものを選びましょう。 ぶどうは軸(上)側の方が、下側より甘いそうです。 |
||||||
●ぶどうの保存方法 ぶどうを保存する場合にはポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室に入れ、なるべく早く 食べるようにしましょう。 冷やしすぎると味が落ちるので、食べる直前に冷やすのがオススメです。 |
||||||
| 栄養課 | ||||||
| TOPへ戻る | ||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
また、古くから色々な薬効が認められていて、ガン抑制効果があるだとか、 最近では、アトピー性皮膚炎や花粉症などのアレルギーの症状緩和に効果がある などと言われて注目されているそうです。 その他、しその香りの成分の中には強い抗菌作用、防腐効果を持つものがあり、 刺身のツマや、料理のあしらい、薬味に欠かせないのはこのためです。
●青じそと赤じその違い ・青じそは、別名「大葉」とも言います。初夏から盛夏にかけてが本来の旬ですが、 年中出回っています。 爽快な香りがあり、刺身のツマの他、天ぷらや薬味等に利用されます。 βカロチンは青じその方が赤じそより多いとされます。
・赤じそは、6月〜7月が旬で、この時期以外はほとんど出回りません。 梅干や紅しょうがの着色、漬物等に利用されます。 青じそがβカロチンなどの栄養成分が多いのに対し赤じそは薬効があると 言われています。
●栄養吸収の良い料理法 青じそは、βカロチンが多いので、油を使って炒めたり揚げたりすると ビタミンAとしての吸収が高まります。 また、魚のフライや天ぷらなどに青じそを巻いてから揚げると臭みも取れて 一石二鳥です。 また、細かく刻むことで、香りがよく出てきますし、パスタなどに和えて 食べると量もたくさん食べる事ができます。
梅干の色付けに使った赤じそは乾かして細かく刻むとごはんにかけるふりかけ (ゆかり)として利用できます。
●しその選び方 色が鮮やかで変色しておらず、葉先までピンとしているもの、しそ特有の香りが 強いものを選びましょう。 大きくなりすぎたものは、味も香りもあまり良くないので注意しましょう。
●しその保存方法 出来るだけ早く使い切ってしまうのが良いのですが、冷蔵庫で保存する時には 湿らせたキッチンペーパーなどにくるんで、密閉容器になどに入れておくと、 4〜5日は保存可能です。
色々な効果があり夏にピッタリの食材「しそ」をたくさん料理に取り入れて、 今年の夏を乗りきりましょう。 |
||||||||||||
栄養課 |
||||||||||||
| TOPへ戻る | ||||||||||||
|
||||||
●夏バテ解消にはビタミンB1、B2やクエン酸が必要 暑い夏には食欲が落ちて、そうめんやざるそばなど、喉ごしのよい麺類に 偏りがちです。 しかし、麺類(炭水化物)だけを食べてもエネルギーには変わりません。 それどころか、体内で疲労物質の元となる乳酸や脂肪に変わってしまい、 ますます夏バテへ…という悪循環になってしまいます。
そこで炭水化物をエネルギーに変えるには、ビタミンB1、B2、クエン酸を 一緒に摂取する事が必要なのです。 |
||||||
●ビタミンB1、B2をたくさん含む食材 |
||||||
|
||||||
|
||||||
麺類と一緒にこれらを摂取するようにすると夏バテ予防に良いですね。 ぜひ試してみてください。 |
||||||
〜行事食の紹介〜 7月4日にデイサービスで愛知県の名古屋名物「ひつまぶし」を実施しました。 天ぷらにはハモを使っています。ハモも夏を感じる魚ですね。 |
||||||
 |
||||||
|
||||||
【ひつまぶしの食べ方】 しゃもじで御飯を十文字に切る。 まず、1/4を茶碗によそって、そのまま食べる。 次に、1/4を茶碗によそい、薬味をのせて食べる。 さらに1/4を茶碗によそい、だし汁をかけて食べる。 そして最後の1/4を自分の好きな食べ方で食べる。 |
||||||
※「だし汁をかけて食べるのが珍しい。サラサラいける!」と高評価でした。 夏バテにも嬉しい「うなぎ」を使ったメニューです。 |
||||||
7月7日には七夕そうめんを実施しました。 七夕らしく、星型☆★☆のコロッケをメニューに取り入れてみました。 願いが叶うといいですねぇ。 |
||||||
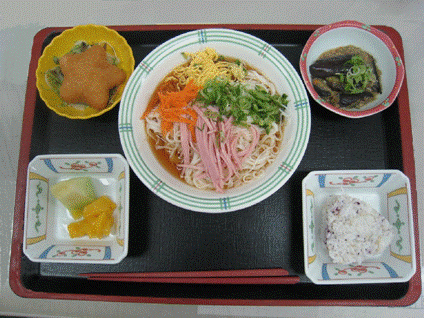 |
||||||
(栄養一口メモ) ・おにぎりには実は玄米もブレンド(1割程度)されています。
・麻婆なすには豚ひき肉も入っていて、これも炭水化物&ビタミン B群の同時摂取による夏バテ予防メニューですね。 |
||||||
|
||||||
| みなさまも、夏バテしないように、おいしく食べて、元気に過ごしてください。 | ||||||
|
||||||
栄養課 |
||||||
| TOPへ戻る | ||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
 |
||||||||||||
|
||||||||||||
次に4月に実施した行事食のご紹介をします。
・4月19日、デイサービスで、お花見の行事食として、バイキングを実施しました。 |
||||||||||||
|
||||||||||||
・4月28日、特養で花見の行事食として、散らしずし御膳を実施しました。 |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| TOPへ戻る | ||||||||||||
 |
||||||||||
新年度を迎えました。 4月1日からの特養新館オープンに伴い、栄養課でも毎日が慌ただしく過ぎて いっています。 それでも、新しい入所者様とも、また新たな関係を築いていける事をうれしく 思う毎日です。 同時に、やはり利用者様の大きな関心事の一つとして、食事の存在がいかに大きい かという事も改めて感じる毎日でもあります。ご期待に添えるよう、出来る限り 頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、今回の栄養だよりでは、「春といえば=たけのこ」 そうです、たけのこについてのお話をしたいと思います。
|
||||||||||
◆たけのこの栄養 血糖値の上昇を防ぎ、コレステロールの排出を促す働きがあります。 よって、食物繊維の摂取は大腸癌や糖尿病、高血圧、動脈硬化を予防する働きがあります。 さらに食物繊維は、胃や腸の中で水分を吸収して膨らみ、満腹感を与える作用から、 摂取により、過食を防ぎ、ダイエットにも効果的であると考えられます。 また、カリウムを多く含んでおり、体外へ塩分を排出するのにも役立ちます。 さらに、たけのこに含まれるアミノ酸の一種「チロシン」は脳を活性化させるのに役立ちます。
|
||||||||||
|
||||||||||
・3月23日、出張握り寿司で、大幸寿司さんが来所して下さいました。 厨房では、お寿司が食べられない方のために、粥の握りずしを作りました。(写真) 今回は、トロ(刻んであるもの)もネタに入れてのリニューアルバージョンとなりました。 やはり、握り寿司は利用者様の気分を高揚させてくれました!!
|
||||||||||
 |
||||||||||
栄養課 |
||||||||||
| TOPへ戻る | ||||||||||
|
||||||||||||
3月といえば 桃の節句「ひな祭り」ですね。 |
||||||||||||
 |
||||||||||||
みずきでは、現在、感染性胃腸炎の予防策として、二枚貝の提供を中止しているため、 |
||||||||||||
| 次にご紹介するのは、2月に実施した行事食についてです。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
あっという間の平成22年度でした。 |
||||||||||||
| TOPへ戻る |
|
|||
|
|||
◆恵方巻きの食べ方 |
|||
今年はみずきでもデイサービス、特養にて恵方巻きを巻く予定です! |
|||
最後に載せた写真は『1月1日に特養で実施したおせち料理』です。 |
|||
|
|||
| TOPへ戻る |
|
|||||||
新年明けましておめでとうございます |
|||||||
昨年度も色々な行事をしました。 |
|||||||
| 「くらしき作陽大学 食文化学部 栄養学科」より実習生の方2名が来られました。 12月8日にデイサービスで、実習生による、利用者様参加型のおやつづくりとして「みたらし団子づくり」を実施しました。 |
|||||||
|
|||||||
絹ごし豆腐と白玉粉を用いた団子で、とても軟らかくできていて、利用者様からも大変好評でした。 |
|||||||
12月24日デイサービスで『鍋パーティー』を実施しました。 |
|||||||
|
|||||||
| 12月25日デイサービスで『クリスマス行事食』を実施しました。 | |||||||
|
|||||||
カニ散らしずし、松茸のお吸い物、特大エビフライと鶏の唐揚げ、カニグラタン、 抹茶ゼリーの白玉あんみつ…と彩りよく、美味しく頂きました。おやつは利用者様と一緒にクリスマスケーキづくりをしました。 |
|||||||
| 12月26日特養で『クリスマス会&誕生日会』を開催し、ケーキバイキング&クリスマスケーキづくりを実施しました。 | |||||||
 |
|||||||
12月28日デイサービスで『餅つき大会』がありました。 |
|||||||
|
|||||||
| 今年もよい1年になりますように… 栄養課 | |||||||
| TOPへ戻る |
![]()
当ホームページに掲載されているあらゆる内容の無許可転載・転用を禁止します。
Copyright(C) 2007 Tokuyou Mizuki
![]()